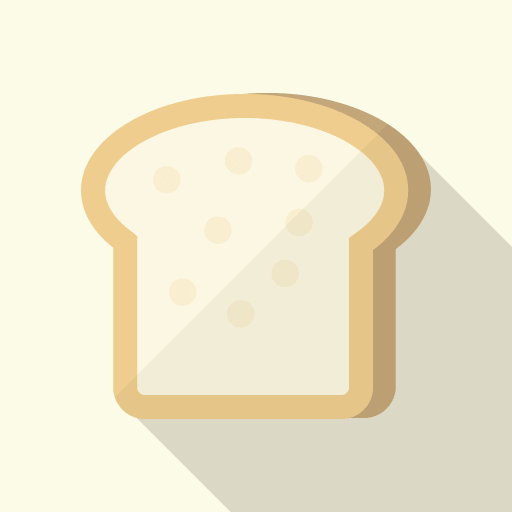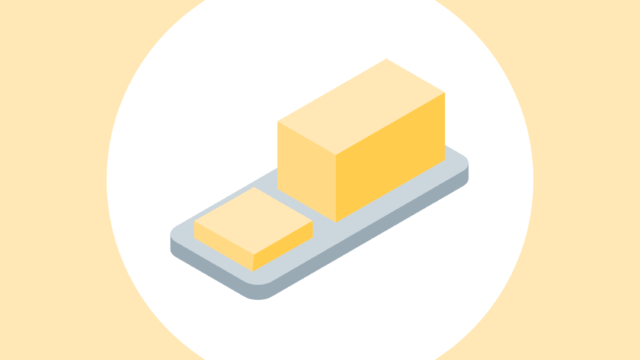この記事では
「湯種ってなに?」
「湯種の作り方」
「湯種を作るときの注意点」
について解説していきます。
『湯種』ってどういうものなんだろう?
湯種を混ぜると『もちもち』とした食感のパンになるよ。
何年か前から、スーパーやパン屋さんで
『湯種食パン』や『湯種製法』というものを
よく見かけるようになりました。
YouTubeでも
『湯種食パンの作り方』
なんて動画をよく見かけます。
一体、『湯種』とは何なのでしょう?
また、お家で『湯種パン』を作るときは
どんなことに気をつければ良いのでしょう?
ちなみに
Pascoの『超熟』や、ヤマザキの『超芳醇』は
湯種を使っているんですよ。
だからあんなにもっちりとして美味しいんですね。^^
湯種とは
湯種とは小麦粉とお湯を混ぜたもの
『湯種』とは、一言でいうと
小麦粉と『沸騰したお湯』を混ぜたもの
のことです。
湯種で作るパンの特徴
『湯種』でパンを作ると
- もちもちした食感になる
- 小麦の自然な甘みが出る
- しっとりして、口溶けが良くなる
- 時間がたってもパサつきにくい
という効果を得られます。
湯種って
ちょっとしたひと手間なんですが
そこから得られる効果は、とても大きいです。^^
湯種の正体って?!
湯種の正体は、小麦粉の『糊化』
小麦粉とお湯を混ぜると
生地がねばねばとした状態になります。
これを
小麦粉の『糊化』と言います。
湯種=小麦粉の糊化
というわけですね。
糊化とは
糊化とは『デンプン』が『糊状』に変化すること
湯種とは、小麦粉が糊化した状態のことだと言いましたが、
この【糊化】についてもう少し詳しく解説したいと思います。
小麦粉の主成分はデンプンです。
糊化とは、デンプンと水を合わせて加熱することで、デンプンがドロドロとした糊状に変化することです。
身近な例で言うと、炊き立てのご飯がまさにデンプンが糊状に変化した状態になります。
およそ小麦デンプンの糊化は、55〜85℃くらいの間で起こります。
そのため、湯種を作る際は、小麦粉とお湯を混ぜて、こね上がった時の温度を55℃以上にしなければなりません。
こね上がったときの温度が低いと、上手く糊化できてないため、湯種としてちゃんと機能してくれません。
湯種の作り方
湯種はどのくらいの量作ればいい?
どのくらいの量の湯種を作れば良いかというと、
パンを作る際の、小麦粉の全体の5%〜30%ほどを湯種にします。
例えば、小麦粉200gつかってパンを作る場合は、10g〜60gの小麦粉を使って湯種を作ります。
お湯はどのくらいの量加えればいい?
湯種を作る際に、小麦粉に加えるお湯の量はどれくらいが良いかというと、
小麦粉の1.5倍のお湯を加えると良いです。
例えば、小麦粉30gに対してなら、45gのお湯を加えると良いです。
湯種を作るときのコツ
では、どうすれば湯種を上手く作ることができるのでしょう?
とても当たり前のことになってしまうのですが、
こね上がった時の温度を55℃以上にするために、次のことをやると良いと思います。
- 先に小麦粉を計量しておく。
- 前もって【ヘラ】を手元に用意しておく。
- 火傷しないよう軍手などを着用しておく。
- 粉を入れたボウルを湯煎で温めておく。(鍋でお湯を沸かす時に、ボウルを鍋の上に乗せて温めておくとよいです。)
- お湯をよく沸騰させる。
- お湯を加えた後、手早く混ぜる。
小麦粉を常温で保管していた場合、
小麦粉の温度は、室温と同じくらいです。(仮に、25℃くらいだとします。)
そこに沸騰したお湯(95℃程度)を加えた場合、
出来上がりの生地の温度は、小麦粉とお湯の温度の中間の、60℃くらいになります。
ちょっと手間取って時間がかかってしまったり、ボウルが冷えていたりすると、
出来上がりの温度が、すぐに55℃以下になってしまいます。
上で書いたコツは、一見当たり前のことに思えるのですが、
湯種を上手に作ろうと思ったときには大切なことになります。
湯種パンを作るときの注意点
①湯種の量は、小麦粉全体の5%〜30%以内にする。
例えば、小麦粉200gを使ってパンを作る場合には、小麦粉200gのうち10g〜60g(全体の5〜30%)を湯種にします。
これは、あまり湯種の量を多くしすぎると、とても扱いづらい生地になってしまうためと、焼き上がりの食感が重たくなってしまうためです。
湯種を使った生地は、ベタベタとして扱いにくく、
また、こねてもなかなかまとまってくれません。
そのため、こね時間が長くなってしまったり、生地丸めや成型といった作業が難しくなってしまいます。
また、湯種の量を多くすると、それだけグルテンの量が少なくなるため、焼き上がりの膨らみが悪くなり、食感が重たくなってしまいます。
このため湯種の量は、多くても小麦粉全体の30%までが良いと思います。
②小麦粉に加えるお湯の量は、白い粉は1.5倍、全粒粉では2倍にする。
湯種を作る際、小麦粉と同じ量のお湯では、生地が硬すぎてとても混ぜづらいです。
生地が硬くて混ぜるのに時間がかかってしまうと、こね上がりの温度が低くなってしまって、湯種の糊化が起こらなくなってしまいます。
普通の白い小麦粉の場合は、小麦粉の1.5倍のお湯
全粒粉の場合は、より多く水分を吸収するので2倍のお湯を加えます。
③湯種は、パンをこねて焼く日の前日に作る。
前日の夜に作っておき、冷蔵庫で一晩寝かせたものを使うと良いです。
時間をおくことで、生地の熟成と水和が進み、
それによって、出来上がりのパンの甘みや旨味が増します。
また、生地が落ち着くので、扱いやすくなります。
湯種をつかったパンのレシピ
実際に湯種を使ったパンのレシピは、よろしければこちらをご覧ください。
[kanren id=”13″]
[kanren id=”526″]
まとめ
湯種のメリット:もちもち食感のパンを作ることができる。
デメリット:生地がベタベタして扱いづらくなる。
作るときの注意点:よく沸騰したお湯で作る。
以上が湯種の説明になります。
湯種で作ったパンは、もちもちしていて、とてもおいしいです。
是非、湯種をつかってパンを作ってみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考図書
パン「こつの科学」:吉野精一 著
パンづくりに困ったら読む本:梶原慶春、浅田和宏 共著
この2冊があれば、パン作りの疑問はほとんど解消されます。
特に、「パンづくりに困ったら読む本」は、基本的なパンのレシピも何点か掲載してあって、写真もたくさんあってとても分かりやすいです、
さらに、読んでいる人が思う疑問についても細かく解説してくれているので、本当におすすめの本です。
家庭でパン作りをされる方は持っておいて損はない本だと思います。